 カメフジツボ
カメフジツボ アカフジツボ
アカフジツボ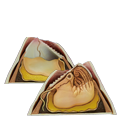 アカフジツボ(分割)
アカフジツボ(分割) クロフジツボ
クロフジツボ チシマフジツボ
チシマフジツボ シロスジフジツボ
シロスジフジツボ ミネフジツボ A
ミネフジツボ A ミネフジツボ B
ミネフジツボ B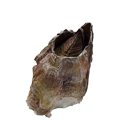 ミネフジツボ C
ミネフジツボ C カメノテ A
カメノテ A カメノテ B
カメノテ B スジエボシ
スジエボシ ミョウガガイ
ミョウガガイ
フリーワード検索
キーワードで検索します。試験導入中です。
閉じるclose
 カメフジツボ
カメフジツボ アカフジツボ
アカフジツボ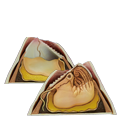 アカフジツボ(分割)
アカフジツボ(分割) クロフジツボ
クロフジツボ チシマフジツボ
チシマフジツボ シロスジフジツボ
シロスジフジツボ ミネフジツボ A
ミネフジツボ A ミネフジツボ B
ミネフジツボ B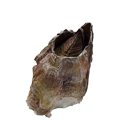 ミネフジツボ C
ミネフジツボ C カメノテ A
カメノテ A カメノテ B
カメノテ B スジエボシ
スジエボシ ミョウガガイ
ミョウガガイ PAGE TOP
PAGE TOP